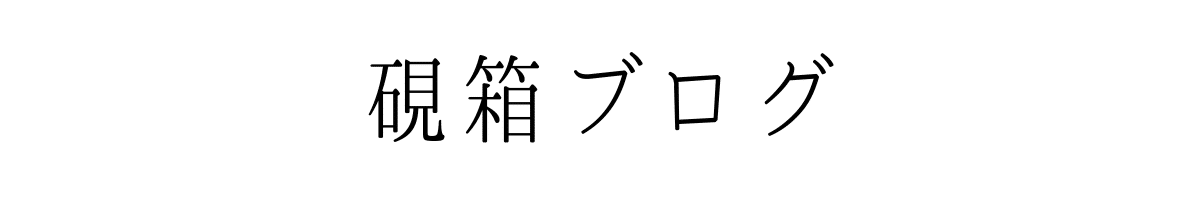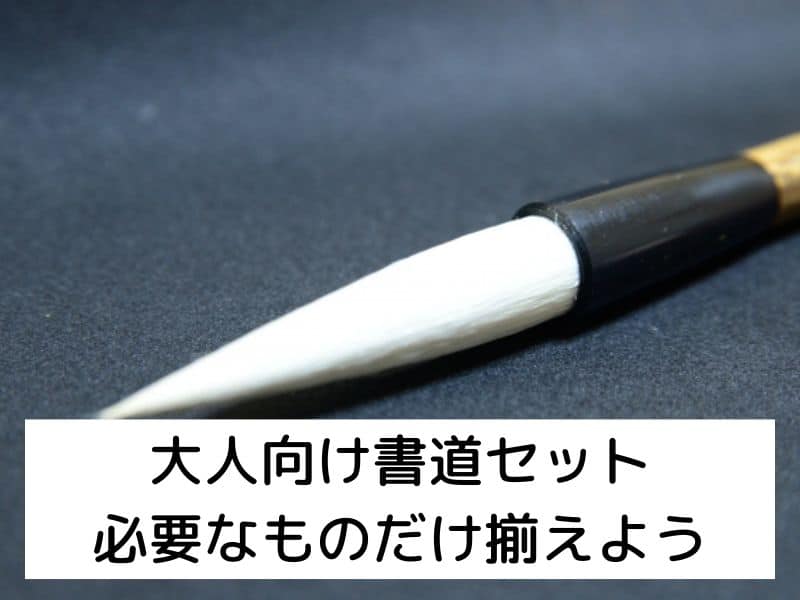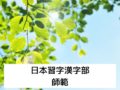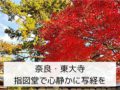「子ども向け習字セットはイヤだけど、本格的なものも要らない」という、初心者の方は多いと思います。
私も、そうでしたから。

あなたに必要なものだけを選んでみましょう!
家で練習したり、教室に持って行ったり。
そんなときに必要なものをピックアップしてみました。
もし、先生から道具の指定があれば、それを使ってくださいね。
教室によっては、入会キャンペーンなどで道具がプレゼントされることがありますので、ご確認ください。
また、お子さんから大人まで、どなたでも長く使える「習字バッグ(?)」も後半でご紹介しています。
ご参考までにどうぞ!
持ち運び用のケース:呉竹「書道用具収納ケース」

仕切り板が動かせて、2種類の硯のサイズに対応



①が五三寸(ごさんずん:約150 × 90mm)の硯を入れたところ。
②が四五平(しごひら:約 135 × 75mm)の硯を入れたところ。
仕切り板が移動でき、しっかり硯をおさえてくれます。
ですから、運ぶときに硯がカタカタと動きません。
五三寸(ごさんずん)・四五平(しごひら)とは
硯の規格のこと
五三寸(ごさんずん): 約150 × 90 mm
四五平(しごひら): 約135 × 75 mm

今まで、これの古いタイプを約10年(子どもも含めて)使っていました
硯:プラスチック製
-300x225.jpg)

すみません、汚れがとれなくて(;^_^A
液体墨だけなら、プラスチック製でも大丈夫
表と裏で、墨を一応磨ることができる面と、液体墨をたっぷりためられる面があります。
大きめの筆を使う場合は、四五平(しごひら:約 135 × 75mm)より五三寸(ごさんずん:約150 × 90mm)の方がいいかもしれません。
これはとても軽いので、書道用具収納ケースに入れた状態で使った方が安定感があります。
動きがダイナミックな方(笑)は、注意が必要かも。
硯の表面には鋒鋩(ほうぼう)といって、細かい凹凸があります。そのために墨を磨ることができるのですが、墨を磨らないなら、この鋒鋩はないほうがよいのです。毛をそろえるために硯に触れるたびに、毛が消耗してしまうからです。
人気商品の一つに「両面硯」が販売されています。セラミックでできていて、片面は墨を磨れ、片面は墨が磨れない、液体墨用のものです。墨を磨らないなら、硯と決めずに、食器やプラスチック製のものなどを自由に使ってよいでしょう。
天来書院編著『筆墨硯紙事典』天来書院、2009、p.150より

書道家のYouTubeをご覧になることがあれば、液体墨を何に入れているか、チェックしてみてくださいね。
石の硯以外も、よく使われています。
先生は、固形墨派?それとも液体墨派?
-e1673068313406.png)
硯は、石の方がいいんじゃないの?
墨は、磨らなくていいの?
先生によっては、「固形墨しか認めない!」こともあるそうですので、事前にご確認くださいね。
固形墨を磨るのって、心がとても落ち着きます。
しかし、初心者のうちは、書くことだけで精一杯。
私は、大人の書道教室で漢字を書くとき、墨を磨ったことがありません。
仮名を習うようになってから、ようやく墨を磨るようになりました。
ということで、使っていない大きめの石の硯が2つも家にあります。
文鎮:ケースに入る長さのものを

1本でも、2本組でもいいので、ケースに入る長さのものを。
大筆・小筆

兼毛(けんもう)が、おすすめです。
適度な硬さがあるので、書きやすいと思います。
兼毛(けんもう)とは[兼毫(けんごう)とも言います]
兼毛の名の通り剛毛と柔毛の混ざり合った筆です。柔剛兼毛には、同じ獣毛の柔らかい毛と硬い毛を混ぜたものや、異なった獣毛を混ぜ合わせたものなど種類も豊富です。羊毛の割合が多いとやわらく、馬、狸、鹿の割合が多くなると弾力があり強い筆となります。
広島筆産業株式会社ホームページ「筆の選び方」より
筆巻
通気性が大事なので、竹を糸でつないだタイプがいいと思います。
下敷
厚さは2mmが、おすすめ。
無地タイプと罫線入りタイプがあります。
罫線入りといっても、実はいろいろ種類があって。
名前用スペースや周囲の余白の取り方など、様々なパターンが存在します。
買う場合は、書くものに合わせないと無駄になってしまいますので、事前にご確認を。

結局、買っても使わなかったものがあります・・・
「罫線入り下敷は、ダメ!」という先生もおられる、とか。
もし、分からないときは、「無地」が無難です。
▼罫線入り下敷きは、タイプがいろいろありますので、事前によくチェックしてくださいね。
→書道の下敷きって、どんなタイプがあるの?【罫線入り下敷き編】
液体墨

作品用と練習用が、あります。
作品用は、液を乾かすと、水で濡らしても溶けません。
作品として提出するものは、作品用を使うように指示されると思います。
作品用の方が高価ですので、おうちで書くだけなら、特にこだわらなくていいですね。
全部合わせて、8,000円以内が目安かも
私のように「大きめの石の硯が、家で眠ったまま」という方が、一定数おられる気がします(笑)
「必要なものだけをそろえる」というコンセプトで、ご提案すると。
「固形墨を使わず、液体墨だけで半紙サイズを書く」場合、以下のお値段が大体の目安かと思います。
40代後半から書道を再開して9年目の、私の経験上の数字ですので、ご参考までに。
| 携帯用ケース | ~700円 |
| 硯(プラスチック製) | ~500円 |
| 文鎮(ケースに入る長さ) | ~500円 |
| 大筆・小筆(ともに兼毛) | あわせて~3,500円 |
| 筆巻(竹製) | ~800円 |
| 下敷(※無地または罫線入り、厚さ2mm) | ~800円 |
| 作品用液体墨(200㏄) | ~800円 |
| 半紙(100枚) | ~500円 |
| 合計 | ~8,000円 |

2025年現在、筆が値上がりしています・・・
持ち運びに必須のバッグ:自立型がおすすめ

自立するので、物の出し入れが簡単

「書道の道具をどうやって持ち運んだらいいんだろう」とお悩みのあなたへ
道具を出し入れしやすい形を選んでみました。
バッグの入口部分にファスナーやフタがあると、物の出し入れに手間がかかりませんか?
「ファイルボックスのような形が使いやすいかも」と思っています。
これなら自立するので、机や椅子などに置いても倒れる心配をしなくてすみます。
道具がスッキリ入ります


下敷き・半紙・新聞紙などを半分に軽く折って、その中に携帯用ケースをはさめば、バッグに収めやすく、紙にシワがつきません。
A4サイズがスッポリ収まるので、家の棚にも置きやすい!
もし墨で汚れても、湿らせた布で拭けば、きれいになります。
おまけ:お子さんにもおすすめの習字バッグ
我が家の子ども用に使っていたのが、B4サイズの、このバッグ。
前の「自立型バッグ」と同じ収納方法で、道具一式が収まります。
持ち手の長さを変えられる2WAYタイプ
手提げにも肩掛けにもなるので、使いやすい方を選べます。
習字以外にも使える
小学校と中学校の書写の授業が終わると、習字バッグって要らなくなりますよね。
でも、このバッグなら他の用途に使っても違和感がありません。
もともと小旅行やビジネス用として作られているもので、とても丈夫です。

子どもと私、合わせて10年使いました。
大切に使えば、かなり長持ちしますよ。
まとめ
大人用の書道セットが、いろいろ販売されています。
じっくり中身を確認すると、自分では使わないものも含まれていたり・・・
少し面倒ですが、自分でひとつひとつ選べば、無駄がありません。
バッグもあなたのお気に入りのものを選べば、気分も上がりますよね↑
必要なものがあれば、その都度買い足していけば、十分間に合いますヽ(^。^)ノ
おすすめ記事
私が普段使っている、液体墨2種類を比べてみました。
よろしければ、こちらもどうぞ!